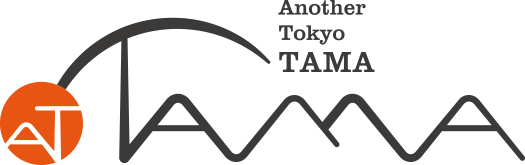秋の祭り
秋という字は、穀物を表す「禾」(のぎへん)に、収穫物を乾かしたり害虫を追い払う意味の「火」と書きます。その名の通り秋は収穫の季節。春に豊作を祈ったお礼に神様への感謝の思いをこめて、古来より、日本の「秋祭り」は、神輿(みこし)、山車(だし)、屋台などが街を練り歩いたり、神楽(かぐら)、獅子舞(ししまい)や土地に伝わる芸能を奉納するなど、多彩な秋祭りが行われてきました。
多摩地域には、まだまだ個性豊かな祭りが残っています。高く澄み渡る空の下、郷土に伝わる芸能や江戸情緒が残る催しに触れてみませんか。


「酉の日(とりのひ)」とは、十二支に定められた12日ごとに訪れる日のことで、新年を迎える前の11月の「酉の日」は「おおとり」という名前の神社の例祭で、各地の神社では縁起物の熊手を売る店が出て賑わいます。その起源は江戸時代に、農民が豊作に感謝し鶏を奉納したことに始まるともいわれています。

吉祥寺の「武蔵野八幡宮」は、吉祥寺駅から北へ10分、五日市街道に面して吉祥寺のほぼ中央に鎮座する八幡宮です。ここでは、11月の「酉の日」に「おおとりさま」とも呼ばれる「酉の市」が立ちます。「おおとり」は大鳥、鷲、大鷲などの漢字が充てられますが、この日には、縁起物の「熊手」(くまで)を売る露店が出て、威勢の良い掛け声や手締め手拍子や拍子木の音が響き、年の瀬の風物詩として知られています。今回は年の瀬に

三鷹市の静かな住宅地に鎮座する野崎八幡社。毎年10月8日の夜には、眼病に効くとされる不思議な団子を求めて、多くの人が集まる伝統行事「だんごまき」が開催されます 。今回は、三鷹市の文化財にも指定されているこの珍しいお祭りについてご紹介します 。

JR国立駅から南へまっすぐに伸びる、幅約44メートルの町のメインストリート「大学通り」の甲州街道を渡ってさらに南にある「谷保天満宮」では、毎年11月3日に「庭燎祭(おかがら火)」が行なわれます。今回はこの炎に圧倒される祭りをご紹介します。

「小宮神社」は、あきる野市草花にある鎌倉時代に建立されたと伝えられている神社です。奉納されている梵鐘(ぼんしょう)は、国の重要美術品に指定されています。毎年秋分の日に行われる小宮神社の例祭日では、「三匹獅子舞」が奉納されます。この記事ではこの小宮神社の「獅子舞」について紹介します。